出しゃばりすぎる母? (3)昔アルファベットには母音はなかった…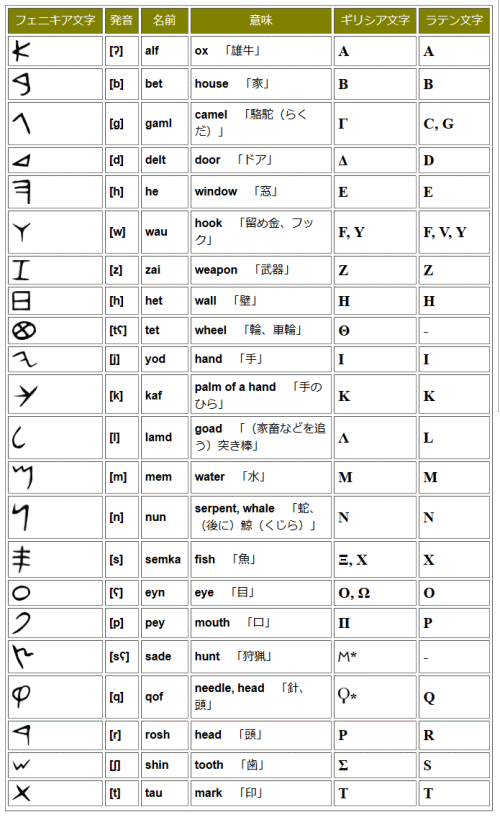 ちょっと話はそれますが、アルファベットのルーツはご存知フェニキア人
ちょっと話はそれますが、アルファベットのルーツはご存知フェニキア人 母音がないので、厳密には「アルファベット」 というのは、子音の組み合わせでざっくりとしたモノの「概念」を表し、そこに「母音」で味つけをすることで具体的な意味を表す言語だからです。たとえば、文字を強引に英語のアルファベットに置きかえてみると、「 さすがにヨーロッパの言語では、母音をそこまで省略することはできないので、自分たちの言語にない子音を表す文字(例:右図の最初の文字)を母音として使うようになったわけです。それがギリシア語のアルファベットで、ここからラテン語のアルファベットが生まれ、それが英語でも使用されるようになっていきます。 それが、「英語」の発音とどう関係あるのかと言われれば、直接関係はないのですが、要は、日本語以外の言語では、母音の位置づけはそれほど高くないということなのです。 英語の母音もところ変われば変わる当サイトの「世界の英語」―「各国母音一覧表」でも紹介していますが、英語の母音は国や地域によって微妙に異なります。「微妙」にとはいえ、日本人の耳にとっては「ほとんど違う母音」のように聞こえる音もあります。つまり、「母音」というものは、それだけ「一貫性のない、不安定な存在」だということなのです。ここで1つ実験です。次の文章の意味がわかりますか? なんとなくわかりますよね。上は 弱くなったり消えてしまう英語の母音さすがに上の文章ほど母音の音が省略されることはありませんが、英語には強弱のリズムがありますから、日本語のように「アイ・キャン・ゴー」と同じペースで発音してくれません。「アイクンゴウ」といった音になり、図示すると下記のようになります。 
しかも、こういった現象は氷山の一角で、何も特殊な例ではないのです。英語のスピーキング自体がこういう現象で成り立っているわけです。あちこちで、単語の母音が落ちたり、次の単語の子音とくっついたりするので、「母なる音」を求めてしまうととまどってしまうのは当然ですね。音の流れは待ってくれませんので、どんどん先に進んでいきます。いわゆる「わからない音の洪水」状態になって、「もうダメだ、ギブアップ!」となるわけです。 |
 日本人は英語がヘタ?中学、高校、大学と勉強していながら話せないのはなぜ?通訳付けないと日常会話もできない首脳は日本だけ?ともあれ英語は世界語になることは間違いなさそう。ここでは「日本人が英語が苦手なわけ」を分析してみたいと思います。
日本人は英語がヘタ?中学、高校、大学と勉強していながら話せないのはなぜ?通訳付けないと日常会話もできない首脳は日本だけ?ともあれ英語は世界語になることは間違いなさそう。ここでは「日本人が英語が苦手なわけ」を分析してみたいと思います。 |

|

|
Last update May 21, 2019